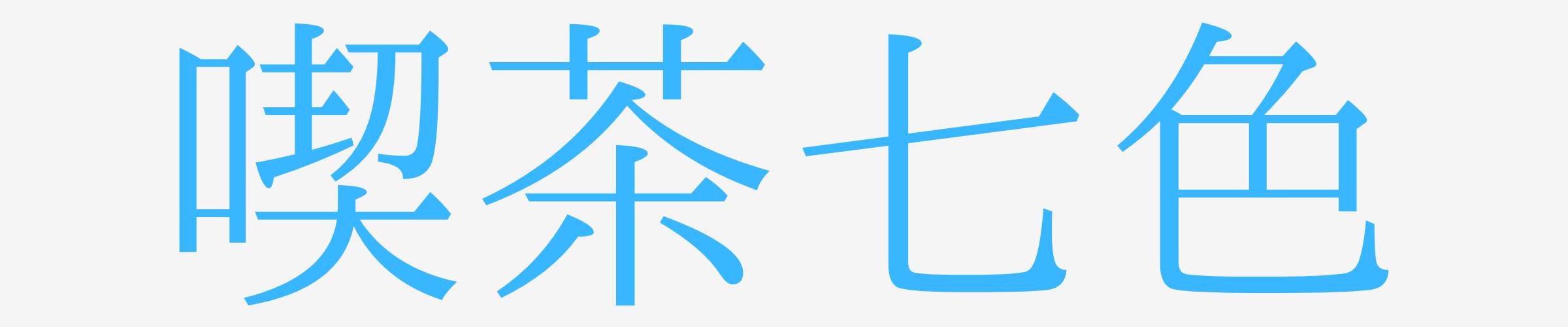今でこそレトロブームで喫茶店に行く人も増えているが、僕が大学生だった10年前くらいは決してそうではなかった。
いつもの喫茶店も60~70代の近所に住む方が多いなかで、カウンターで1人コーヒーを飲む若い大学生の僕は異色の存在だった。
でも、皆さんは孫とは違う関係性で若い人と話せるみたいな感じで、声をかけてくださる常連さんも多かった。
増野さんもそんな1人で、黒縁のオシャレなメガネにいつもシックで上質な洋服を着ているおじいさんだった。
当時の僕は読書にハマり、それこそ1日に1冊のペースで何かしらの本を読み漁っていた。
今はあのときほどではないが、本当に読む体力が有り余っていたのだと思う。それくらいに読書にまみれた生活を送っていた。
ある日、喫茶店に向かうと増野さんがカウンターでコーヒーを飲みながら、ママさんと話していた。
カウンターに常連さんがいると一緒に話したいから、僕は手に持っていた本をカウンターに置いた。すると増野さんが、「君は何を読んでいるんだい?」と声をかけてきて、僕は「◯◯という本を読んでいます」と答えた。
増野さんは目が悪く、今ではほとんど読まないが、昔は大の読書家であったことを話してくれた。
そして、会うたびに「君は何を読んでいるんだい?」と声をかけてくれ、増野さんからたくさんの本を教わった。
ある日は池波正太郎の『男の作法』を勧めてくれて僕はそれを読み、うな重を食べに連れて行ってくださり、本で紹介されている内容と同じ経験をさせてもらうこともあった。
ただ、増野さんの目は少しずつ悪くなっていき、足腰も弱ってきたからお店に来るのも一苦労になる日が多くなり、僕が手を貸して家に送り届ける日もあった。
その日も喫茶店で一緒になり、僕は増野さんを送り届けた。いつもはマンションのエントランスまでなのに、「ちょっと上がっていかんか?」と言われて、僕は増野さんについて行った。
初めて入る部屋は壁一面が本棚になっていて、その圧巻の光景に僕が息を飲んでいると、「君は富山出身だったろう」と棚から文庫本を取り出して、僕に手渡してくれたのが、高橋治の『風の盆恋歌』という作品。
地元の祭りであるおわら風の盆と男女の恋に関する長編恋愛小説だ。当時彼女もいなかった僕にとっては、その本の大人かつ複雑すぎる恋の行方を読むのは大変だったけれど、「ずっと大切にしてきた」という増野さんからいただいた本は今も残っている。
増野さんが今どうしているか僕にはわからない。それは僕だけではなく、ママさんもわからない。
連絡を取る手立てがなく、元気に暮らしているのか、それとも亡くなっているのかわからないのだ。
でも、僕の手元には増野さんに教えてもらった本、いただいた本は変わらず残っていて、それを見るたびに学生時代の記憶が蘇ってくる。
決して今がわかることはなくても、かろうじてつながっているという事実が、色褪せない記憶を作っているような気がする。
喫茶七色|akira