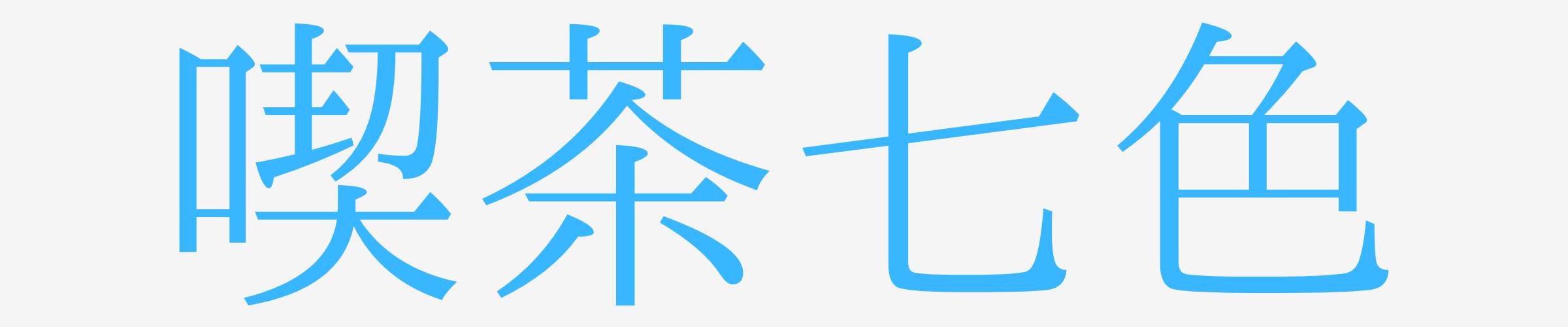母方の祖父母の家は東北の山奥にあり、当時住んでいた場所からは車で1時間ほどで行くことができた。
そんなちょうどいい距離感もあり、孫の顔をすぐ見れることに祖父母も喜んでくれるし、そのまま家に泊まることもしばしばあった。
車もほとんど通らないような道路沿いにある家は畑が広く、裏の山も全部敷地の一部だったので、畑の野菜や山の山菜など年中食材の宝庫のような場所だった。
そんな祖父母の家で一番印象に残っているのは冬の朝食の時間だ。
白い息が出るくらい冷えた朝、床も冬の寒さを吸い取るかのように冷えていて、パタパタと急ぐように大きなダイニングテーブルが置かれた食卓の部屋へと入る。
祖父母はすでに起きていて、祖母はご飯の支度、祖父は薪を入れるタイプのストーブにやかんを載せて、お湯を沸かしてお茶を飲んでいる。
祖母に「もうすぐご飯だから席に座っとき」と言われて座ると、そこで初めて部屋の様子を落ち着いて眺めることができる。
祖母がこちらに背中を見せる形で台所作業をしている。包丁で野菜を切るトントントンと一定のリズムを刻む音。鍋からお湯が吹きこぼれて火に当たってジュワッと弾ける音。
祖父のほうに目をやれば、やかんのお湯が湧き続けていて、シュンシュンとまるで蒸気機関車のような音にも聞こえてくる。
そんな真冬の寒い朝、不思議と食卓のある部屋は温かくて、気がつけば祖母が作った朝ご飯が並んで全員で食卓を囲んだ。
祖父のご飯茶碗は子どもながら信じられないくらいの大きさで、でもそれをいつもおかわりするほど米をよく食べる元気な人だった。
東北、それも北の場所は朝食に筋子が出てくる割合が多い気がする。祖父母の家もそうで、朝食に限らずいつでも冷蔵庫から筋子が入った花柄のホウロウの容器が出てきた。
それを開けると、一口サイズにカットされた筋子がたくさん盛られている。それを炊き立ての白いご飯にのせて、ワシワシとご飯を食べるのだ。
炊きたてのご飯はいっそう白く見え、そこに筋子をのせれば、湯気の中に見える赤色がいっそう際立って見え、キレイなようなそれでいて朝から見るには刺激的な色だったようにも記憶している。
筋子を一口かじれば塩気が口いっぱい広がり、ご飯を口の中に無理に入れるようにかきこむくらいがちょうど良くて、噛んで飲み込むと子どもながらに何と贅沢な朝食を味わっているのだろうと思うのだった。
そうして月日は流れていつの間にか筋子とは無縁の都会暮らしを送っている。
1人で食べるには高級品だし、スーパーで並んでいてもあの大きさを期限があるうちに食べきれるとは思えず、いつもスルーしてしまっていた。
そんな自分にも味方といえばコンビニのおにぎりで、少しいい値段は張るが筋子があるとついつい手が伸びてしまう。
おにぎりをかじれば筋子が顔を出す。でも、子どもの頃のような感動にはない。
やっぱり筋子は湯気が上るほかほか炊きたてご飯にのせて、一気にかきこんで食べるからこそおいしいのだ。すっかりそんなことがあったのも忘れていたけれど、コンビニのおにぎりを食べているとふいに昔を思い出すことがある。
そうして自分の食の記憶も上書きされていくのかもしれない。
でも、昔のそういう食の印象的な想い出は完全に上書きされるわけではない。
それが日常に近かったのなら、なおさら。筋子がおかずの一部だったからこそ、上書きされない大切な食の想い出になっている。
喫茶七色|akira