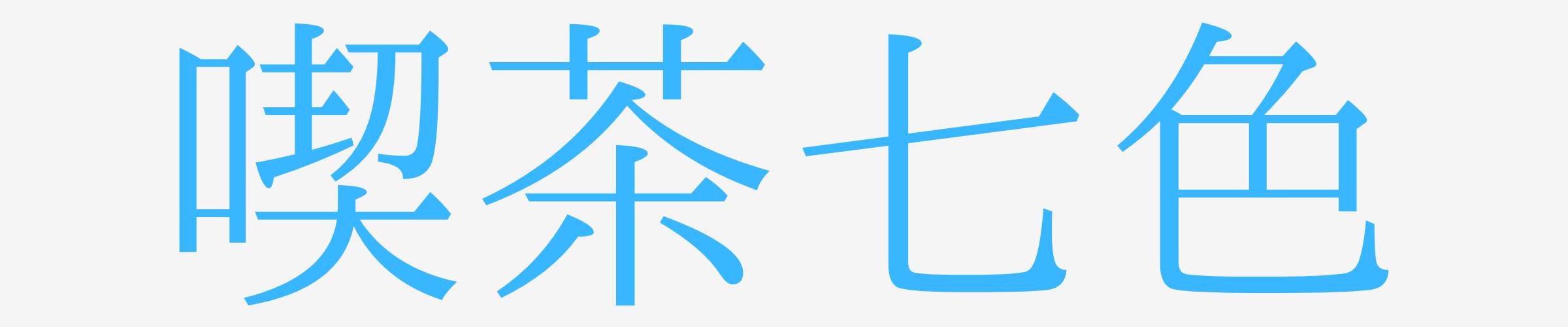朝仕事へ向かう準備をしている合間、スマホに目をやると父から着信が入っていた。
こんな朝早くから電話をよこすことなんて滅多にないから、きっと良くない報せだと思って折り返したら、案の定「Yさんが亡くなったから通夜には出てほしい」という連絡だった。
Yさんというのは父の上司にあたる方で、仕事やそうでないときも含めて、もうかれこれ40年以上の付き合いがある。それは僕も同じで、僕は生まれてから30年近くのご縁だ。
その報せを聞いても僕は正直なところ「年齢を考えればそうか……」程度の認識で、それはどちらかといえば遠い付き合いだったからそう思ったのだろう。
僕にとっては家族でも親戚でもなく、あくまで父の上司という関係性の中だったから、幼少期の記憶はぼんやりとしているし、最後にお会いしたのは父にお伴した2年以上も前のことだ。
仕事を早退して喪服に着替え、急いで会場へと向かう。こういうときに限って電車が途中で止まっており、遅刻するわけにいかないから一駅だけどタクシーを使ってなんとか間に合った。
式場の入口には◯◯家と書いてあり、やっぱりYさんは亡くなったんだと、そこで改めて実感した。というのも、祖父の死が僕にとって初めての身近な死だったのだが、当時は家に着くまで本当に死んだとは思っていなかった。
何おかしな話をと思われるかも知れないが、当時は「死」という現実を否定したくて仕方なく、トラウマのように今も残っていて、そういう経験がフラッシュバックしたのだと思う。
でも、先に会場に入っていた父と母の姿、祭壇に飾られたたくさんの花とYさんの遺影を見たとき、当たり前だけどこの死は現実で、本当にYさんは亡くなったのだという揺るぎない事実を突きつけられた。
焼香も読経も滞りなく終わり、隣の部屋に移って親族や参列者との食事が始まったわけだが、Yさんと父の昔話がおもしろかった。
父は若い頃(多分20代後半くらい)に、Yさんが亡くなるまで暮らしていた一軒家の裏にあるアパートに住んでいた時期があったそうだ。ある年の年末、父は実家に帰らなかったために、Yさんに代わって家を見る役を任されたらしい。ただ、Yさんの家には飼い犬がいたから散歩をする必要があった。
連れて行くと犬はどんどん歩くし、リードを離したらとんでもないことになるから、半端ないプレッシャーと戦いながら、自分が散歩をしているのか、犬に散歩させられてるのかわからない、という話だった。
父の若い頃の話を聞く機会なんてほとんどない(あまり良くないが……)から、その姿を想像すると面白おかしく思えたのだ。
お酒も入り、みんなはYさんとの想い出話に花を咲かせているが、僕はあまり話に参加できるほどでもないので、母に言われてYさんの顔を見に行くことにした。
棺の中のYさんは僕が最後に会った頃と何も変わらない姿で、みんなが口を揃えて言うように、ただ寝ているだけで今にも起き上がるかのようだった。
読経のときも悲しかったけれど、やっぱり顔を見るといろんなことを思い出してしまう。
家族アルバムに入っているYさんに抱っこされている僕の写真、Yさんが当時住んでいたマンションのバルコニーで過ごした時間の記憶、大学進学や就職で挨拶しに行ったとき、そして最後にお会いした日のこと。
Yさんとのいろんな記憶が頭の中をグルグルと駆け巡り、「死」という現実とミックスされて、どうしようもなく悲しくなる。
でも、そのとき、僧侶が読経で読み上げていた、たしか「夜闇を歩く」という言葉を思い出した。
亡くなったらすぐにいわゆる一般的な天国、それはどこか白く明るくふわふわとした平和な場所に行けると思っていたけれど、まずは暗がりの中を歩いていくらしい。そして、導かれるときが必ず来るという。
いつも粋で、男らしく、奥さんを大切にしていたYさんなら、すぐに向こうに行ける気がする。
残された僕ができることといえば、Yさんのことを思い出すことだけだ。
思い出すことが、亡くなった人とつながれる唯一の手段なのだから。
死はとても悲しいことだけれど、悲しんでばかりもいられない。ひとしきり悲しんだあとは、その人の旅立ちを心の中で見送るくらいが僕にできる精一杯の供養なのだと思う。
だから、「さようなら」だけど、同時に「いってらっしゃい」と祈った。
喫茶七色|akira