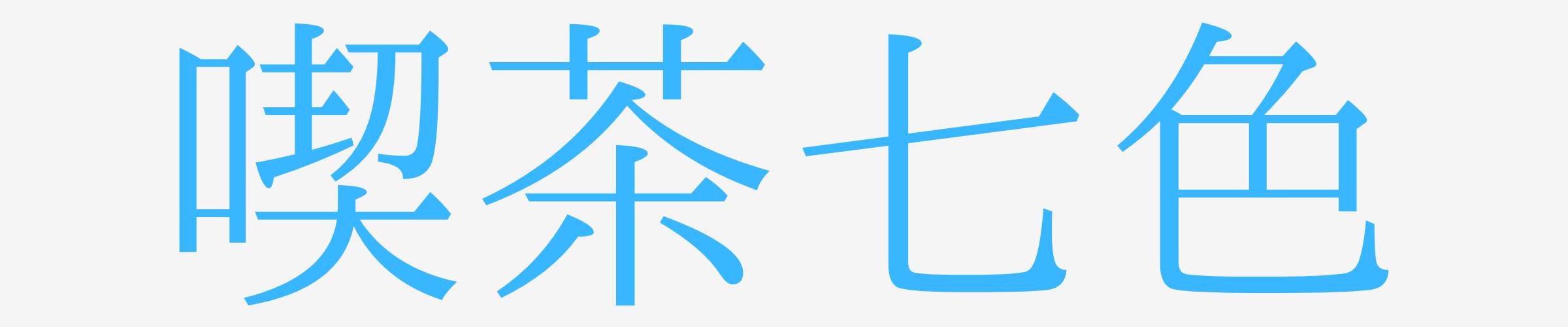僕の大学時代はいつもの喫茶店に入り浸るような生活をしていて、カワモトさんとはそこで出会った。
当時60代で、いつも特徴的な柄のハンチング帽を被り、決まったカウンター席でモーニングを食べたり、たまにはクリームソーダを飲んだりする姿を見かけていた。
「カワモトさん」という名字以外に、お店のママさんや常連さんからは「おひげのオジサン」とも呼ばれていた。
その名のとおり、カワモトさんは立派な口ひげをたくわえており、あごは剃っても口ひげだけは大事に残していて、ハサミを使って自分で整えているような方だった。
生まれも育ちもずっと名古屋。こてこての名古屋弁に中日ドラゴンズ好き。
どこからどう見ても生粋の名古屋っ子。
僕はそんなカワモトさんのことが、はじめは怖かった。遠慮なくものを言うし、その姿が怒ってるようにも思えたから。
でも、それは本人なりの照れ隠しだった。僕のような若い人と交流できるのが嬉しかったらしく、それに気づいてから僕とカワモトさんは仲良くなった。
カワモトさんの家は、僕が暮らしていたアパートから歩いて10分くらいの場所にあり、よく遊びに行くようになった。
そこは自宅兼作業場になっている。もうかれこれ30年以上、メーカーに部品を提供する小さな工場を一人で経営していた。
僕はそんな工場に遊びに行くのが好きだった。
「いつでも来たらいいがね」との言葉どおり、遊びに行くのはいつも突然で、「また仕事の邪魔しに来たのか。ワハハ!」と冗談を飛ばされつつ、いつも優しく迎え入れてくれた。
工場の隣には机が1つと椅子が2つの小さな事務室があり、僕が行くと、カワモトさんは三ツ矢サイダーの缶を冷蔵庫から2本取り出し、1本を手渡してくれる。
「最近どうだ?」と聞かれて、僕は近況をいろいろ話す。カワモトさんはタバコを吸い、サイダーを飲みながら、僕の話を嬉しそうに聞いてくれる。そして、自分のことを話してくれる。それは過去とか今のこととか。
時間が来ると「akiraくん、ぼちぼちやりぃ」とひと言。それがカワモトさんの口ぐせだった。
カワモトさんは、いつもの喫茶店や工場以外に、良いことがあるときは「コーヒー行くぞ」と言い、行きつけの喫茶店に僕を連れて行ってくれるときもあった。
お金を貯めて買ったという、左ハンドルの2人乗りのスポーツカーに乗せてくれて、いつも嬉しそうにハンドルを握っていた。
喫茶店に着くと、お店の方から「あれ?今日は若い人を連れて珍しいですね?」と言われて、カワモトさんは「あぁ、こいつは俺の息子!冗談だよワハハ!」と答えた。
僕も一緒になって笑ったけれど、内心はとても嬉しかった。なぜなら、他人といえば他人の僕を、息子のように思って接してくれることが本当に嬉しかったから。
大学4年生になり、就職も決まり、あっという間にこの街を離れる季節がやってきた。
喫茶店のカウンターで、ママさんやカワモトさんと話す時間も、今はこれが最後。
そう思うと、ふいに涙が止まらなくなった。
「別れじゃない。またいつでも来たらいいがね」と、カワモトさんはいつもの荒い口調でそう言い、僕を送り出してくれた。
社会人になり、1~2年に1回は名古屋に遊びに行くと、そのたびにカワモトさんは喜んでくれ、宿代がもったいないからと、自宅にある離れに泊めてくださった。
そんなある日、スマホの着信履歴にママさんからの電話が入っていた。
普段あまりない方からの連絡は、なんだか嫌な予感がする。残業中だったけれど、電話を折り返す。
たわいもない話のあと、少しの間を空けて「実はカワモトさんがね、亡くなったんです」とママさんはおっしゃった。
その瞬間、頭が真っ白になる感覚が僕を襲い、唇をグッと噛み締めて、震えを抑えることしかできなくなる。
やっとの思いで、「どういうことですか?」と言葉をつなげると、ママさんが話してくれた。
カワモトさんは、90歳を過ぎる自分のお母さんと一緒に暮らしていて、元気だったけどある日突然亡くなった。
カワモトさんの憔悴している姿は誰が見ても明らかで、喫茶店に足を運ぶ回数も急に減ったそうだ。
しばらく姿を見せなくなり、別の場所で暮らすカワモトさんの娘さんが心配して家に向かうと、布団のなかで動かなくなったカワモトさんを見つけたというわけだ。
遺書もなく、自ら命を絶ったわけでもない。
ただ、お母さんを見送ってから1か月後の死は、本当にお母さんを追いかけたかのようだった。
僕が工場に遊びに行くと、たまにお母さんと会うときもあった。
元気だけど少し呆けた様子に、カワモトさんは「本当に困ったもんでしょ」と困り顔で僕に言う。
でも、お母さんの姿を見るその眼差しや横顔が、実はとても優しかったことを僕は知っている。
ママさんとの電話を終えると、カワモトさんとの想い出が急に鮮明になる。
もう会えないことのつらさが押し迫り、涙があふれてくる。
身内以外の死で泣くのは初めての経験だった。
それは、同じ喫茶店に足を運ぶ同士だった僕とカワモトさんが、年の離れた友人であり、人生の先輩でもあり、息子のようでもある関係の深さを証明するかのようにも思えた。
カワモトさんはもういない。けれど思い出すことはできる。それは僕自身の記憶にカワモトさんが残っているから。
行き詰まったときやつらくなると、ふと脳裏に蘇ってくる「akiraくん、ぼちぼちやりぃ」という言葉。
そして、いつもその記憶にいるのは、立派な口ひげをたくわえ、ハンチング帽を被ってタバコを吸う「おひげのオジサン」の姿なのだ。
喫茶七色|akira