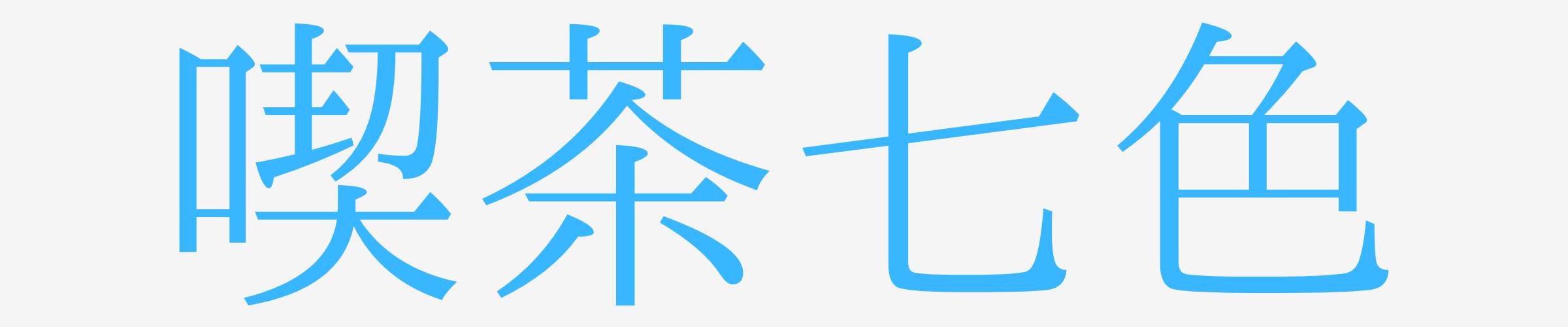そのチャイスタンドは、通りから外れた静かな場所にあった。
3坪くらいの小さなお店は夫婦で営んでおり、行くといつもあたたかく迎えてくれた。
インドへの旅でチャイの魅力に引き込まれ、現地の味にご自身のエッセンスを付け足した唯一無二のチャイは、1杯ずつ丁寧に煮出される。
紅茶の甘い香りとミルクの濃厚な味わいを引き立てるのが、試行錯誤の末に生まれたオリジナルのチャイスパイス。
とてもやさしい味わいで、夫婦の人となりを表しているかのようだった。
僕は2人のことが大好きで、他の人に知られたくないから、お店にはいつも1人で行っていた。

窓際に置かれたシエスタチェアに座るのが好きだった。体をすっぽりと包み込むような座り心地のなか、1杯のチャイを味わうのは、何にも代えがたい贅沢な時間だった。
お店ではよく音楽や旅の話を一緒にしたのを今でも覚えている。

その日は雨が降っていて、他にお客さんもおらず、チャイを飲みながらゆっくりと過ごしていた。
チャイをぼんやりと口に運ぶと、スパイスの香りであることを思い出した。
それは初めての海外で、サンフランシスコに行った時のこと。
僕はなぜか、海外用のSIMやWi-Fiを借りず、ガイドブックも持たないまま日本を飛び出した。
今となってはなぜそうしたかわからない。
必要な情報は日本にいるうちに全部スクショしていたから、それさえあればなんとかなるだろうと思っていたのかもしれない。

でも、現実はやっぱり迷って、サンフランシスコのパウエルという場所で、僕は右往左往していた。
バスは頻繁に来るけれど、目的地に行くか定かではなかったし、運転手や街の人に聞いても、みんな首をかしげてどこかへ行ってしまった。
どうしようかなと思っている矢先、通り沿いにカラフルなビーチパラソルを掲げ、メタル製の台車で何かを売っている小さな屋台を見つけた。
近づくとそれはチャイだった。
売っている方は、褐色肌のとても小柄な女性で、インドから移住してきたそうだ。
1杯3ドル60セント。
チャイは煮出してあり、ポットで保温されている。
お金を払うと、とても大ぶりな紙コップになみなみと注いでくれ、スパイスの香りがふわっと立ち込めた。
その場で飲み、「おいしい」と伝えるとニッコリと微笑んでくれて、僕も嬉しくなった。
屋台を後にしてすぐ、なんとかバスが見つかり、運転手に「◯◯まで行く?」と聞くと、「あぁ、とりあえず乗れ!」と言われて乗り込んだ。
前払い制で支払いの仕方に困っていると、運転手は親指を立てて、「今回はサービスだ。次から払ってくれよ」と伝えてくれた。

無事に宿にたどり着き、その日は安心して眠りにつくことができた。
街にはマクドナルドやスターバックスもあったけれど、あの時たまたま見つけたチャイの屋台に足が向いて良かったなと思う。
だって、遠い異国の地で不安だったのに、1杯のチャイで心が落ち着いたし、良い人もたくさんいると気づけたから。
チャイを飲むたびに、いつも通っていたチャイスタンドの夫婦のことと、サンフランシスコで出会った屋台の女性を思い出す。
どちらも同じチャイにまつわる僕の大切な想い出。
喫茶七色|akira